
皆様の医院では、『忍び寄る医院の収益減少問題』を意識されていますでしょうか?きっかけは、ちょっとした患者数と単価の変化かもしれません。しかし、そういった小さな変化の裏側には、大きな構造的変動が隠れている可能性があります。また、小さな変化も、積み重なれば年間の売上に意外と大きく影響するものです。本稿では、そういった問題を未然に防ぐため、小さな変化を早期に発見する方法を見ていきたいと思います。
例えば、一日平均患者数50名、平均単価550点、1ヶ月診察日数22日の医院があったとします。年間の売上は7,260万円となります。仮に、一日平均3名患者が減少すると、年間では約436万円減収(※注1)。診療報酬の平均単価が仮に30点減ると、年間で約396万円減収します(※注2)。患者数減と平均単価減が両方起こると、808万円の売上減少です。さらに、コストが5%アップしたら、どうなるでしょうか?某医院の収支シミュレーションを図にしましたのでご覧ください。
※注1: 患者数3(人) × 平均単価5500(円) × 22(診療日数/月) × 12(月数/年)=435.6万円/年
※注2: 患者数50(人) × 平均単価減少額300(円) × 22(診療日数/月) × 12(月数/年)=396.0万円/年

図 某医院の収支シミュレーション
「たまたま悪条件が重なっただけ」「うちは大丈夫」と甘く見るのは危険です。人口減少・超高齢化社会が進みつつある現状、この試算はどのクリニックにも顕在化しうるリスクであると筆者は考えています。日本における近代医療史上、「診療報酬単価」「患者数」「コスト」の三つが同時に悪化することは、医療機関にとって初めてのことなのかもしれません。
医院の収支にゆとりが無くなっているなかで、会計士による約2ヵ月後の売上、コスト、収支の報告では対応が遅きに失してしまいます。異変を早期に発見し、異変があった場合はさらにその原因を知り、対策を実行し、対策の効果を検証することが望まれます。
筆者らの調査結果では、約5割から8割の医院経営者が経営分析の必要性を感じています(開業後3年未満の医院では8割、3年から10年未満で5割、10年以上で7割)。なかでも開業3年未満と10年以上の医院経営者の経営分析ニーズが、3年から10年未満のグループに比べて高いですが、これは「不安」「危機感」が高いからだと推測されます。

図 経営分析ソフトが必要だと答えた医院経営者
医院経営のKPI(重要経営指標)
数ある経営と業務に関わる数値のうち、毎日、そして毎月の単位で把握するべき基本の経営指標は、①平均単価、②1日患者数(月単位では平均患者数)、③業務効率(患者数÷勤務したスタッフ数)、④平均待ち時間の4つであると筆者は考えています。
「単価×患者数」は売上であることから、単価と患者数をモニタリングすることで売上の変化を察知できるだけでなく、売上の上下が単価に起因するのか、患者数に起因するのかも把握できます。
医院コストのなかで、人件費が最も大きな割合を占めます。また、人手不足かつ人件費が上昇するなかで、労働生産性を高めることが医院経営の今後の鍵となるのは、間違いありません。業務効率を数値化することで、経営資源で最も重要な「人的リソース」の活用度合いを知ることができます。業務効率は、一日の受診患者数÷その日に出勤したスタッフ数で算出することができます。
待ち時間からは、患者の不満の度合いを推察することができます。待ち時間が恒常的に長くなると、患者数の減少のみならず、医師とスタッフのストレス、残業などのコスト増加にもつながります。
普段から、上記指標の「標準値」をイメージしておくことで、毎日、または毎月のちょっとした変化も敏感に察知することが可能です。標準値は、昨年一年間の平均値、または、昨年の同月の平均値か、目標値と比較しても良いでしょう。
データの取得と分析
レセプトコンピュータ(レセコン)から日々の売上、初診の平均単価、再診の平均単価、全体の平均単価、患者数などを収集することが可能です。レセコンには、その他に病名や実施した検査処置手術等の回数及び診療報酬、患者の基本情報(性別、年齢、住所など)も含まれるため、経営分析のための基礎データとしては貴重なデータソースです。
一部レセコンには、簡単な経営分析ツールや集計機能が含まれていますが、レセコン内のデータだけでは不足であることと、レセコンの集計機能だけでは、直感的に経営の状況を把握しづらいなどの問題があります。よって、現実的には、多くの医院経営者や事務長はレセコンからデータを抽出し、手作業で表計算ソフトなどを使って、分析やグラフ化、リポート作成を行っています。
経営と業務の分析にはある程度のノウハウと経験、そして労力と時間がかかります。日々継続できることではありません。そこで、レセコンとデータ連携して必要なデータを日々自動取得し、さらにレセコンには含まれない業務に関わるデータの入力と管理分析も含めて省力化してくれるソフトが必要になってきました。
筆者の医院では、3Beesの経営分析ソフトであるBeeコンパスを使い、毎日その日の患者数(対前年同月同曜日比)、診療報酬総額(対前年同月平均と比較)、平均診療報酬単価(対前年比較)、勤務スタッフ数、平均待ち時間、業務効率(患者数÷スタッフ数)などを、自動作成されたレポートから確認しています。また、このレポートは、登録されたメールアドレス宛に日々の日報として送信されます。

図 ソフトによるデータ入力と管理・分析
前述の「標準値」「目標値」と実際のデータに乖離があった場合、異変を早期に発見することができ、早期に対応できます。
例えば、平均単価が減少した場合は、減少したのが初診単価なのか、または再診単価なのかを把握し、さらにどの医療行為(検査、処置、手術)が減少しているのかを調べます。患者数が減少した場合は、減少が新規患者か、再来患者かを把握します。新患が変化した場合は、どの媒体を通じて自院を知ったか(例えば、口コミ、ホームページ、看板、タウン誌、口コミサイトなど)を把握することもとても重要です。また、デモグラフィックス分析(年齢分布、居住地)を行い、地域の患者のニーズに応えられているかどうか、ニーズとのアンマッチが起きていないかを確認します。

図 異変を早期に発見するステップ(Beeコンパスの画面で確認)
こういった確認ステップを日々確実に実行し、変化を見える化、異変を早期に発見できるよう開発されたのが3Beesの経営分析ソフトBeeコンパスです。


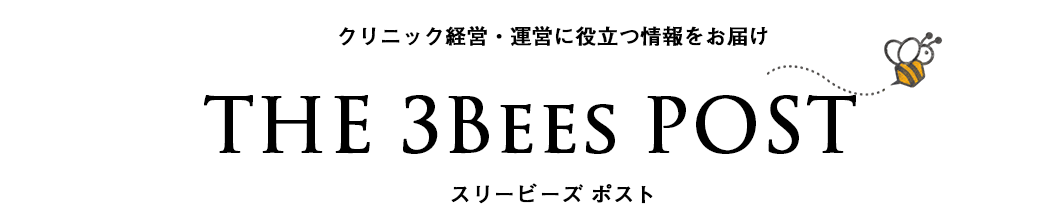


 オプション
オプション